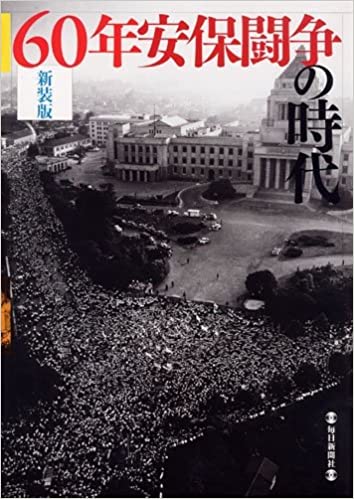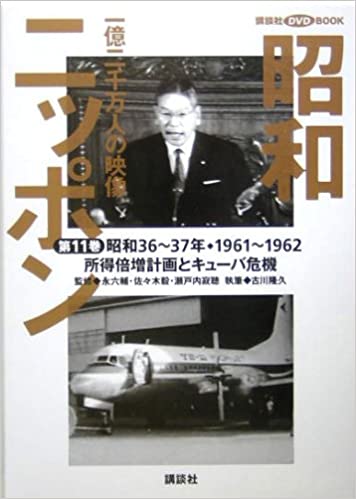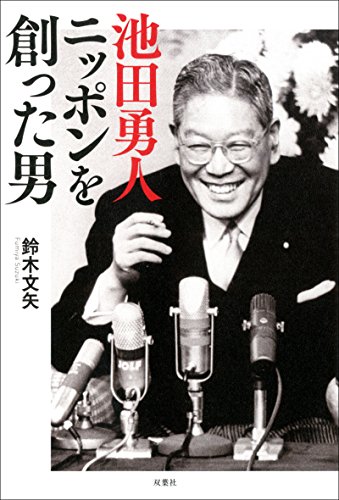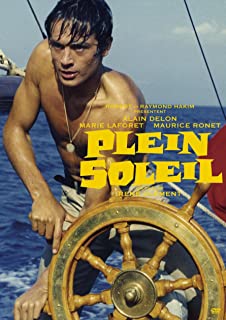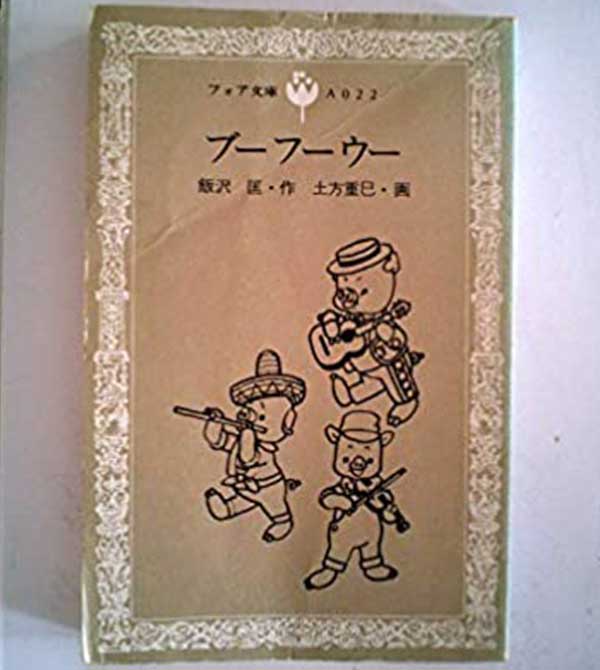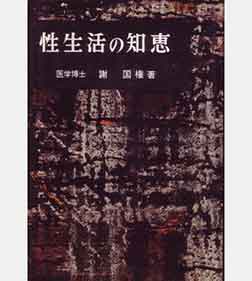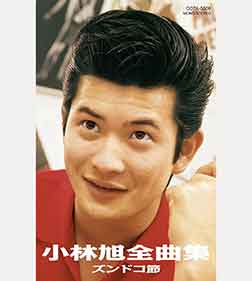出来事
カラーテレビでの放送開始

1960年、日本でもカラーテレビの放送が開始された。
NHKが日本で初めてのカラーテレビ放送を行い、初のカラーテレビ番組は1960年8月28日に放送された「国会中継」だった。
その後、1960年10月1日には、日本のテレビジョン放送(現在のNHK総合テレビジョン)がカラーテレビの本放送を開始し、日本の視聴者もより鮮やかでリアルな映像を楽しむことができるようになった。
カラーテレビの導入により、テレビ業界や視聴者の視聴体験に革命がもたらされ、以降、カラーテレビは日本のメディア文化において重要な役割を果たすこととなった。
60年安保闘争
1951年に凍結された日米安保条約は、ワシントンで1960年1月19日岸首相により改定の調印がなされた。
これに反対した社会党・労働組合・学生(全学連)及び一般市民は「日米新安全保障条約」に抗議し、6月15日、国会議事堂の周りを大規模なデモ行進をした。
8000人を超える学生を動員した全学連は、機動隊と衝突しながらも国会内に突入し中庭を占拠した。
この騒動で、東大の女子大生が死亡するという痛ましい惨事が起きた。6月18日には安保阻止統一行動、33万人が国会を包囲するデモを行ったが、19日午前0時、安保条約・協定、自然承認となった。
画像は「新装版 60年安保闘争の時代 大型本」の販売ページにアクセスできます。
流行語
所得倍増
池田勇人は大蔵官僚を経て、吉田茂に見込まれ自由党に入党。蔵相、通産相などを歴任。1960年(昭和35年)自民党総裁となり、三たび内閣を組織した。
しかし、政治家・池田勇人の発言は度々世間を騒がせることになる。「貧乏人は麦を食え」「私は嘘は申しません」などは当時、国民の間で、流行語となった。
そして、そんな彼が発した世紀のキャッチコピーと言われるのが、所得を10年で2倍にするという「所得倍増政策」だった。
池田は内閣総理大臣の座に就くと、"所得倍増計画"を掲げ、日本を高度成長の波に乗せていく。
画像は「昭和ニッポン〈第11巻〉所得倍増計画とキューバ危機―一億二千万人の映像 (講談社DVD BOOK) 単行本」の販売ページにアクセスできます。
トップ屋
私は嘘を申しません
昭和32年、自らの政策集団である宏池会を旗揚げ、派閥の長となる。
昭和35年、安保闘争の結果岸内閣が倒れると、自民党第四代総裁に就任、内閣総理大臣となる。
安保騒動後の不穏な政情のなか「寛容と忍耐」のキャッチフレーズで、国民との対話姿勢を重視し、また、「所得倍増計画」の経済重視を打ち出した。
ある時、国会答弁時に細かい数値をあげて即座に説明したところ、嘘をつくなと言われたが、調査してみるとその数値は正確であったことから、池田自身のキャッチフレーズが「嘘をつかない」となる。
その後、1960年の総選挙の際に自民党のテレビCMで「私は嘘は申しません」と発言し、この言葉は当時の流行語となった。
画像は「池田勇人 ニッポンを創った男」の販売ページにアクセスできます。
おもちゃ
映像作品
太陽がいっぱい(映画)
フランスの巨匠ルネ・クレマンが監督を務め、パトリシア・ハイスミスの小説を映画化したサスペンス。
イタリアに金持ちの道楽息子を連れ戻そうとやって来た貧しい青年が、激情にかられてある犯罪を思い立つ姿を甘美な調べに乗せて映し出す。
本作でアラン・ドロンは鋭利な刃物のような危うい美貌と抜群の演技力を披露。映画音楽の名匠ニーノ・ロータの音楽によって際立つ、凶暴なまでの青春の狂気に惑わされる。
主演のアラン・ドロンは本国フランスを中心にヨーロッパで人気を博したが、1960~1970年代の日本でも、爆発的な人気を誇っていた。
画像は「太陽がいっぱい 最新デジタル・リマスター版」のDVD販売ページにアクセスできます。
ブーフーウー(TV人形劇)
書籍
性生活の知恵
「性生活の知恵」という本は、1960年に出版された。
この本は、性に関する様々な情報やアドバイスを提供するもので、当時の人々にとってはタブーとされていたテーマに取り組んだ先駆的な書籍だった。
性生活についての正しい知識や技術を伝え、夫婦間の関係を深めるためのヒントを提供している。
さまざまな性的ニーズや問題に対処し、より満足度の高い性生活を実現するためのアドバイスが掲載されている。
また、心理学や医学の観点からも性に関する健康的なアプローチを提示している。
この本は、当時の社会において性に関するオープンな対話を促し、性教育の重要性を強調する一助となった。その後も、性教育や性に関する情報提供の重要性が広く認識され、この本はその一翼を担うこととなった。
画像は、謝 国権さんの著書「性生活の知恵」の販売ページにアクセスできます。
ヒット曲
アカシアの雨がやむとき
ズンドコ節/小林旭
軍歌のひとつといわれることもあるが、実際のところは戦地に赴く男たちの本音を歌った流行歌のようなもの。
炭鉱や漁港で歌われていたリズムを元に門司出身の学生M・K氏が作曲したものとされている。
作詞・作曲者が不詳であり権利上の問題が発生しないため、多くの歌手によってリメイク版が製作されている。
1960年に小林旭がカバー。
『海から来た流れ者』シリーズの第2弾『海を渡る波止場の風』のテーマ曲として誕生した。
歌詞は大きく変わり、曲のテーマは「若い男女の恋物語」となった。
元々は小林の『アキラの鹿児島おはら節』のB面曲であったが、こちらのほうがヒットした。
画像は「小林旭全曲集 ズンドコ節」の販売ページにアクセスできます。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■