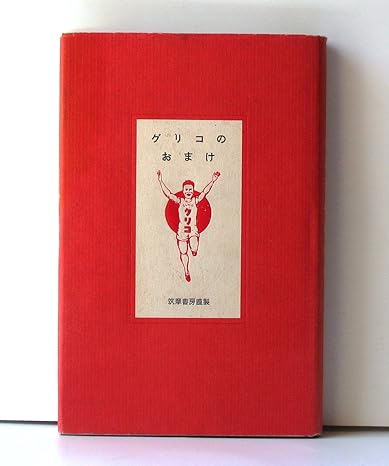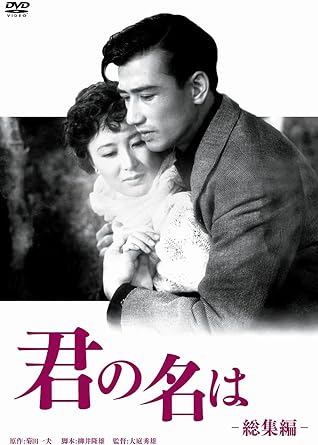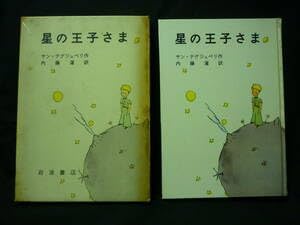出来事
NHKが日本で初のテレビジョン本放送を東京で開始

1953年(昭和28年)2月1日午後2時にNHKは東京・内幸町のNHK放送会館で日本で初のテレビジョン本放送を開始した。 当時は1日の放送時間は午後2時~午後4時、週3回、視聴可能エリアは東京23区とその周辺、テレビカメラはわずか5台しかなく、フィルム取材によるニュースや劇場映画などを除き大部分の番組が生放送だった。 また、受信機(テレビ)台数は約700台、受信機価格は当時の大卒初任給の約3倍だった。 日本初のテレビジョン本放送開始は、日本のメディア史、文化史において重要な出来事で、テレビの普及は、人々の生活、社会、文化に大きな変化をもたらした。
流行語
コネ
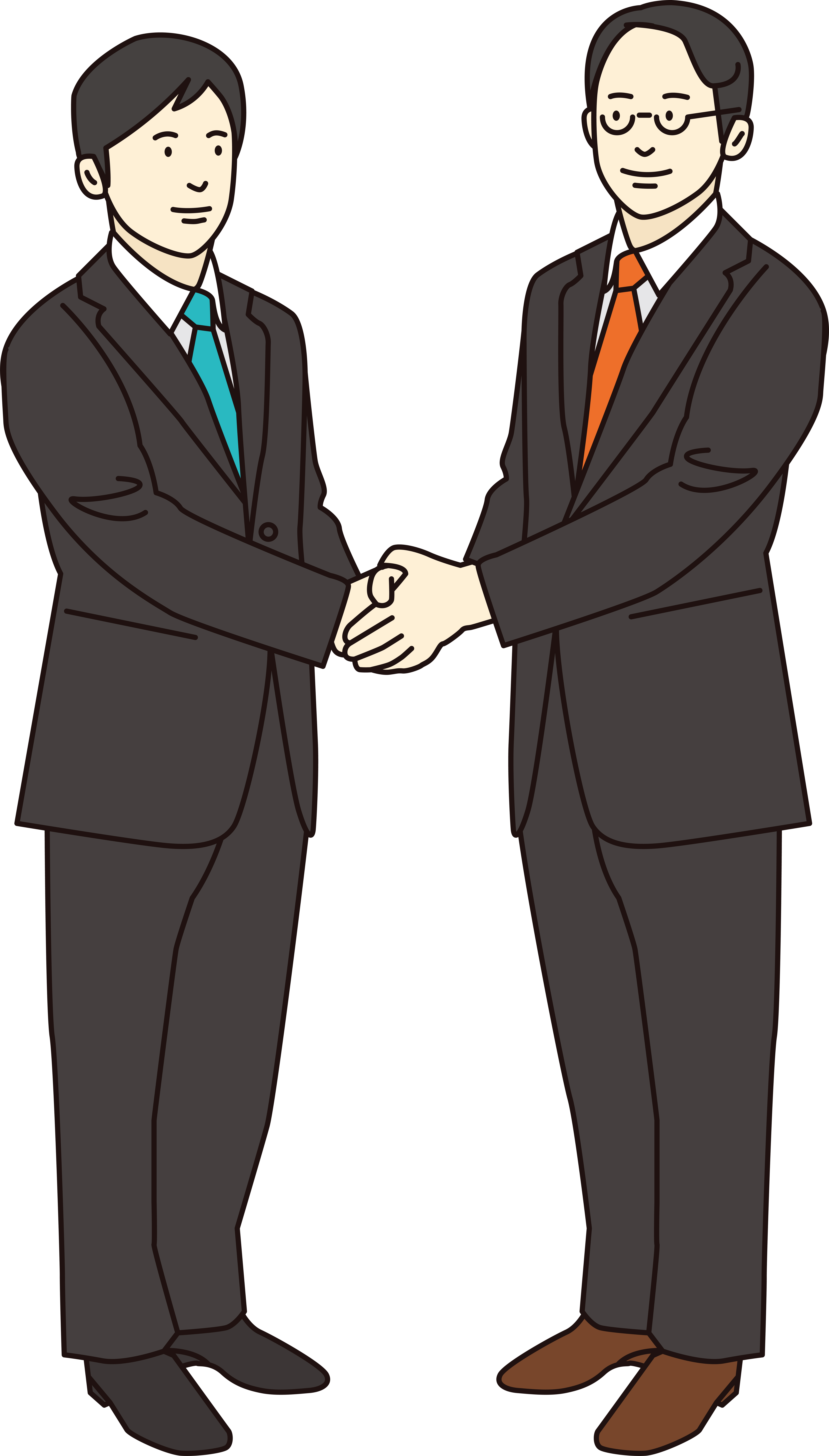
1953年、日本では「コネ」という言葉が流行したが、これは「縁故」や「関係」という意味で使われ、特に仕事や人事の舞台で重要視された。
その背景としては、戦後の復興期において、資源や物資の不足があったため、人間関係や人脈がビジネスの成功に大きく関わるようになったことが挙げられる。さらに、元々、日本の文化や社会構造において、人間関係やつながりを重視する傾向があったことも、コネの流行を後押しした。
政治や大企業の役員人事などの場面でコネが重要視され、特に旧来の組織や会社では、出身大学や家族の地位、政治的なつながりなどが人事の決定に影響を与えた。仕事の契約や取引も、人間関係や縁故が関与しやすい状況で行われることが多く、日本では、「コネ」が重要視される時期が長く続いた。
その後、社会の変化やものの見え方の変化により、人事や取引の判断基準が変わっていき、現在でも人間関係は重要だが、公平性や能力の評価も求められるようになり、コネの持つ影響力は以前ほどではなくなっている。
街頭テレビ
「街頭テレビ」という言葉が流行したのは、1953年頃から1964年頃までの約10年間程である。当時、テレビは高価な家電製品であり、一般家庭に普及するにはまだ時間がかかっていた。そこで、テレビをまだ持っていない人々がテレビ番組を楽しめるように、駅前や繁華街・商店街・デパート前・公園などの公共の場所にテレビを設置したのが「街頭テレビ」である。
テレビは、当時はまだ高価なものであり、多くの人が所有していなかったため、街頭テレビは多くの人にとってテレビを見る貴重な機会で、ニュースやスポーツ中継などの番組は、人々にとっては新しいエンターテイメントの一つとして大変な人気だった。特にスポーツ中継では、街頭に集まった人々が一体感を味わいながら試合を観戦する様子が見られた。
1950年代後半からテレビが家庭に普及し、個々の家庭で番組を楽しむことが一般的になると、徐々に街頭テレビは姿を消していった。
画像は「週刊昭和(No.29) 昭和28年(1953) 街頭テレビ」の販売ページにアクセスできます。
おもちゃ
映像作品
君の名は
1953年は、日本映画史に残る名作が数多く公開された年であるが、その中でも「君の名は」は、公開前から大きな注目を集め、映画館の入場券は売り切れ続出となり、当時としては異例の大ヒットとなった。大映東京撮影所で製作され、監督は小津安二郎、脚本は野田高梧であるが、特に主演の佐田啓二と岸惠子を大ブレイクさせ、2人の人気が不動のものとなった。
さらに、終戦直後の東京で、進駐軍将校と日本人の恋愛を描いた作品として当時としてはセンセーショナルな内容であった為、この作品によって、進駐軍に対する複雑な感情を持つ人々から様々な議論が巻き起こり、大きな社会現象となった。
また、「真知子巻き」を代表に、劇中で岸惠子が着用していた服装は、多くの女性に真似され、当時のファッションや流行にも影響を与えた。
画像は「君の名は 総集編」のDVD販売ページにアクセスできます。
書籍
星の王子さま
フランス人の飛行士・小説家であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの小説である。彼の代表作であり、1943年にアメリカで出版され、日本では1953年に岩波書店から出版され、翻訳者は内藤濯である。日本でも出版後すぐに人気となり、2022年現在、200以上の国と地域の言葉に翻訳され、世界中の大人から子供までに愛されている作品だ。
星の王子様には、人生に役立つヒントがたくさん詰まっている。大切なものは目に見えないもの、愛することの大切さ、想像力の大切さなど、人生を豊かに生きるためのヒントを与えくれる。
また、寓話的な要素も持ち合わせていて、物語に登場する様々なキャラクターは、人間の様々な側面を表しており、読者に自分自身を見つめ直すきっかけを与えてくれる。
サン=テグジュペリ自身による独特なイラストが描かれてるが、これらのイラストは、物語の世界観をより一層豊かにしてくる。
画像は「星の王子さま サンテグジュペリ.内藤濯岩波書店函入り」の販売ページにアクセスできます。