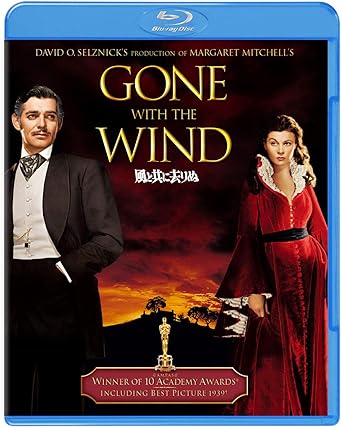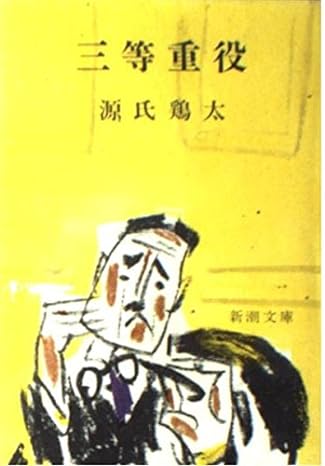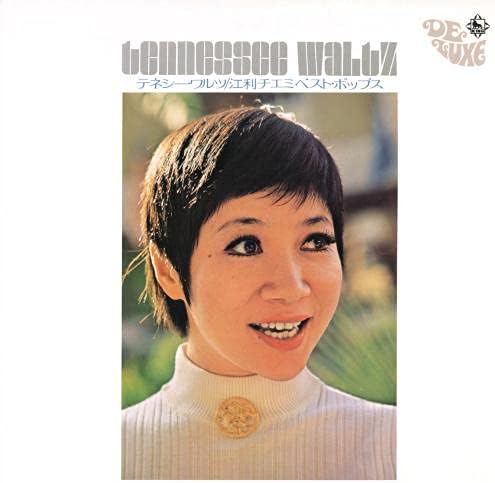出来事
第1回NHK紅白歌合戦放送
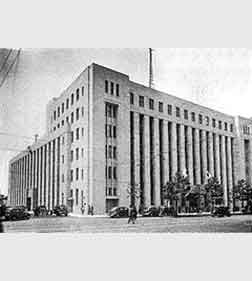
1951年1月3日、正月のラジオ番組として「NHK紅白歌合戦」スタートした。3回目までは、東京・内幸町の放送会館第1スタジオから、夜8時から9時までの1時間、生放送された。あった。番組は何がとび出すか分からない「Xアワー」で、出場歌手・趣向などは一切発表されなかった。紅組は渡辺はま子、白組の藤山一郎がそれぞれキャプテンとなり男女各7名、総勢14名の歌手が会場に招待された約300人の観衆の前で歌を披露した。初優勝の栄冠は白組に輝き、リーダー藤山一郎を中心に「エイ・エイ・オー」の勝ちどきがわき起こった。 第4回からは、より多くの観客に公開するために会場を大劇場に移そうとしたが、正月はどの劇場も公演等で空いておらず、やむなく年末に開催せざるをえなかった。これ以降、「紅白歌合戦」は年末恒例となった。
流行語
言うてみてみ 聞いてみてみ
恐妻家

妻に頭の上がらない、妻を恐れる夫の事を差す。
恐妻家という表現は、1924年(大正13年)三田村鳶魚著の「春日局の焼餅競争」の中の記述で「二代将軍も随分な恐妻家であります」と既にあり、また1938年に徳川夢声が共済組合のもじりで「恐妻組合」と洒落で言った言葉もあったが、1952年に流行語として評論家・大宅壮一氏が流行らせた言葉である。
おもちゃ
ブリキの自動車(セダン型自動車)

1952年日本で大変よく売れたおもちゃは、ブリキの自動車だ。当時、日本は朝鮮戦争特需で景気が良く、子ども向けの玩具も盛んに生産されていた。ブリキの自動車は、手頃な価格で壊れにくく、ゼンマイで動くことから、爆発的な人気となった。
当時の新聞記事によると、1952年のクリスマスシーズンには、ブリキの自動車が全国的に品薄状態になり、デパートでは開店前から長蛇の列ができるほどだった。
ブリキの自動車以外にも1952年頃人気があったおもちゃには、ブリキの人形・ブリキ製電車・プラモデル・糸電話・万華鏡・ケン玉・メンコなどがある。
これらの玩具は、戦後の物資不足が解消し、子どもたちの生活が豊かになったことを象徴するものと言えるだろう。
映像作品
風と共に去りぬ(映画)
風と共に去りぬは、南北戦争前後のアトランタを舞台に、炎のような女、スカーレット・オハラの波乱万丈な半生を、完璧なまでの配役と、この上ないほどの豪華なセットや衣装を用いて描いたロマンスの金字塔的作品である
1952年9月4日、東京・有楽座、大阪・松竹座から全国ロードショー。 世界で30番目の上映。 当時ロードショー料金が200円だった頃、『風と共に去りぬ』は有楽座・松竹座では全館指定席、600円・500円・300円の超高額料金にもかかわらず、大当たりした。
監督:ヴィクター・フレミング、原作:マーガレット・ミッチェル、出演:ヴィヴィアン・リー、クラーク・ゲイブル、レスリー・ハワード、オリヴィア・デ・ハヴィランド、トーマス・ミッチェルでアカデミー9部門(作品・主演女優・助演女優・監督・脚色・撮影・室内装置賞・編集賞にタールバーグ記念賞)を受賞し、ハリウッド映画史上不滅の最高傑作と言われいる。
画像は「風と共に去りぬ」のBlu-ray販売ページにアクセスできます。
書籍
「三等重役」源氏鶏太/著
小説『三等重役』は、源氏鶏太が1951年(昭和26年)8月12日号から1952年(昭和27年)4月13日号まで、週刊誌『サンデー毎日』(毎日新聞社)で連載。タイトルが流行語になった小説であった。
「三等重役」とは「サラリーマン重役」のことで、創業社長でもオーナー社長でもなく、一般社員と意識的にも能力的にもさほど変わりのない人物が取締役、あるいは社長になったことを指し、源氏鶏太の本作によって広まった語である[1]。本作の場合は、前社長が戦争協力者とされて公職追放され、思いもよらなかった人物が社長になる話である。
単行本は、1951年のうちにまず1冊目が毎日新聞社から刊行され、翌1952年に『三等重役 続』、『三等重役 続々』が刊行された後に、同年『合本三等重役』が刊行されている。
1957年(昭和32年)には新潮文庫に採用された。
本作は映画化され、「三等重役」を演じた河村黎吉もさることながら、それに振り回される人事課長を演じた森繁久彌に人気が集まり、シリーズ化された。
森繁を映画スターにした最初の作品であり、原作の源氏鶏太も、『新・三等重役』を同じ『サンデー毎日』誌に1958年(昭和33年)11月2日号から1960年(昭和35年)6月19日号の長きに渡り連載することとなった。それにともない、1959年(昭和34年)には森繁を主演に『新・三等重役』が映画化され、シリーズ化された。
画像は「三等重役 源氏鶏太/著」の販売ページにアクセスできます。
ヒット曲
テネシーワルツ 江利チエミ
リンゴ追分 美空ひばり
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■